大田区、品川区の弁護士事務所。経験豊富で身近な法律事務所
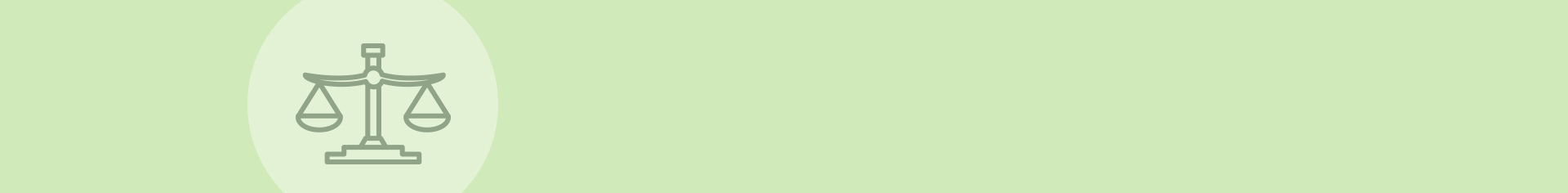

相続・遺言
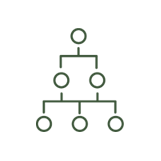
相続問題
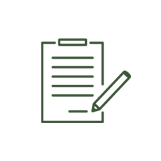
遺言書作成
相続や遺言のご相談はとても多く、様々なご相談が寄せられます。
ご家族間のもめごとに困っている方、相続の手続きの進め方が分からない方など、お気軽にご相談ください。
まだ考えるには早い、と思っても先々のことを考えておくことは重要です。
残されるご家族の事も考え、問題が起きないように配慮しましょう。
ご家族間のもめごとに困っている方、相続の手続きの進め方が分からない方など、お気軽にご相談ください。
まだ考えるには早い、と思っても先々のことを考えておくことは重要です。
残されるご家族の事も考え、問題が起きないように配慮しましょう。
こんなお悩みご相談ください。
「遺産分割の話し合いがまとまらない・・・」
「そろそろ遺言書を作成したいと思うのですが、よく分からない」
「相続の手続きが必要なのですが、何から始めたらいいのか分からない」
「どんな遺産があるのか、関係者が多すぎて分からない」
「遺産分割調停を申し立てられてしまった」
「遺言書の内容に疑問があるのですが、どうにもならないのでしょうか?」
「相続の手続きをしないとどうなるのでしょう?」
「遺産の情報をきちんと開示してもらえない」
よくあるご相談
贈与を受けた相続人との預貯金債権の共同相続
Qestion
私には兄がおりますが、兄は父からマンションの購入資金を出してもらうなど多額の援助を受けております。この度、父がなくなりましたが、父の遺産は預貯金だけです。父から多額の援助を受けている兄が、遺産の預貯金を折半する遺産分割を求めてきましたが、兄の提案には納得できません。
どうすればよいでしょうか(ちなみに母は10年前に他界しております)。
Answer
従来は、預貯金債権については、相続と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるというのが裁判所の考え方でしたので、遺産が預貯金だけの場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることもできない取り扱いでした。このような従来の取り扱いでは、あなたの兄の預貯金を折半するという遺産分割の提案に問題はないということになります。
しかしながら、平成28年12月19日の最高裁判決で、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与を受けて特別受益があるという場合の不公平を是正するという背景を踏まえて、最高裁判所は、従来の判例を変更して、遺産が預貯金だけの場合でも遺産分割の対象となるという判断をしました。
したがって、現在では遺産が預貯金だけの遺産分割の申立てを家庭裁判所は認めていますので、兄の提案に納得できないあなたは、遺産分割調停申立てをして、兄が受けた多額の援助を特別受益と主張することで、兄より預貯金を多く取得することができることになると思います。
不動産の評価と遺留分侵害
Qestion
父が亡くなり公正証書遺言があることがわかり、その遺言に従うと、兄は実家の不動産(相続税評価額約5000万円)と預貯金約1000万円、私は預貯金約2000万円を取得することになります。兄は父の遺言が私の遺留分(遺産総額の4分の1=2000万円)を侵害していないから、この内容で遺産分割協議書を作成することを求めてきました。私としてはどう対応したらよいでしょうか。
Answer
遺留分の算定に際しては、不動産の評価が必要ですが、不動産の評価は『時価』で行ないます。『時価』とは、相続税評価に使われる土地の路線価や建物の固定資産税評価額ではなく、公示価格や不動産業者の査定する実勢価格が『時価』に近いというのが通例です。
したがって、実家の不動産を時価評価して5000万円以上の評価となり、遺産総額の4分の1が2000万円以上の金額になれば、あなたの場合、遺留分を侵害されたことが認められます(例えば、実家の不動産の時価が8000万円とした場合は、遺留分は遺産総額の4分の1=2750万円であり、あなたは遺言書では2000万円の取得しか認められてないので、不足の750万円について兄に請求が可能です)。
そこで、兄との話し合いが困難であれば、家庭裁判所に遺留分侵害の調停を申し立てることになります。
法定相続人が多数の甥姪である場合の相続手続
Qestion
伯父伯母に子供がおらず兄弟も全員亡くなっており、法定相続人が兄弟姉妹の子ばかり10人以上いますが、不動産や相当額の預貯金があります。どのように遺産分割したらよいでしょうか。Answer
遺留分の算定に際しては、不動産の評価が必要ですが、不動産の評価は『時価』で行ないます。『時価』とは、相続税評価に使われる土地の路線価や建物の固定資産税評価額ではなく、公示価格や不動産業者の査定する実勢価格が『時価』に近いというのが通例です。
したがって、実家の不動産を時価評価して5000万円以上の評価となり、遺産総額の4分の1が2000万円以上の金額になれば、あなたの場合、遺留分を侵害されたことが認められます(例えば、実家の不動産の時価が8000万円とした場合は、遺留分は遺産総額の4分の1=2750万円であり、あなたは遺言書では2000万円の取得しか認められてないので、不足の750万円について兄に請求が可能です)。
そこで、兄との話し合いが困難であれば、家庭裁判所に遺留分侵害の調停を申し立てることになります。
遺産分割協議に応じないただ1人の相続人との交渉
Qestion
私を含め法定相続人が複数おりますが、1人の相続人を除き全員が親の面倒を見ていた私が全て相続すればよいという意見です。しかし、親から勘当されて疎遠になっていた兄1人が法定相続分の権利を主張しており、遺産分割協議が成立させられずに困っています。Answer
遺留分の算定に際しては、不動産の評価が必要ですが、不動産の評価は『時価』で行ないます。『時価』とは、相続税評価に使われる土地の路線価や建物の固定資産税評価額ではなく、公示価格や不動産業者の査定する実勢価格が『時価』に近いというのが通例です。
したがって、実家の不動産を時価評価して5000万円以上の評価となり、遺産総額の4分の1が2000万円以上の金額になれば、あなたの場合、遺留分を侵害されたことが認められます(例えば、実家の不動産の時価が8000万円とした場合は、遺留分は遺産総額の4分の1=2750万円であり、あなたは遺言書では2000万円の取得しか認められてないので、不足の750万円について兄に請求が可能です)。
そこで、兄との話し合いが困難であれば、家庭裁判所に遺留分侵害の調停を申し立てることになります。
内縁夫婦と財産の承継
Qestion
正式な婚約届を出していない内縁夫婦で子がいない場合、配偶者名義の財産は法定相続人である配偶者の親や兄弟姉妹のものになってしまいますか?Answer
内縁夫婦の場合、公正証書遺言で配偶者に遺贈しておくべきですが、正式な遺言書がなくとも最低限、配偶者への贈与の意思を表したメモ書きを作成しておけば、残された配偶者の権利にすることは可能です。内縁夫婦と居住権
Qestion
内縁の夫と共同でマンションを購入し長年住んでいますが、先日、夫に先立たれてしまいました。このまま住み続けることはできるでしょうか?Answer
夫が死亡した場合に内縁の妻が、共有建物の居住が継続できるかどうかという点については、特段の事情がない限り、夫婦の一方が死亡した後は他方がその不動産を単独で使用する旨の合意が成立していると推認されるという判例がありますので(最高裁判所:平成10年2月26日判決)、法定相続人に対し、当面、住み続けることを主張することは可能です。遺言と遺留分
Qestion
母が亡くなり(父は20年前に他界)、長女の私と弟の2名が相続人ですが、母は全ての財産を弟に相続させるという公正証書遺言を作成していました。私はどうしたら母の財産を相続できるでしょうか?Answer
お母さんが遺言によっても自由に処分できない財産(遺留分)があなたには認められます(具体的遺留分は、子が相続人の場合、相続財産の2分の1に法定相続分【本件では2分の1】を乗じた割合)。但し、遺留分を認めさせるには、遺留分権を行使する意思表示を相続開始及び遺言等を知ったときから1年以内に配達証明付内容証明郵便等で(後の訴訟等で証拠とするため)、行う必要があります。相続人の遺留分を侵害する遺言等があることを知って放置すると、相続することができなくなります。
Contactお問い合わせ
法律やお手続きでお困りの方
お気軽にご相談ください。

受付時間 平日9:30~17:30
